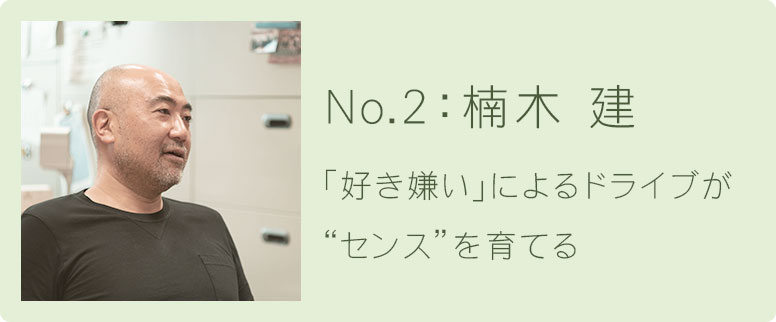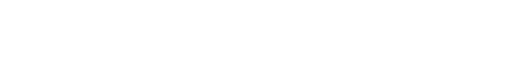今回は、一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻(ICS)で教鞭をとられる鈴木先生にお話しを伺い、ブランドとは何か、それを育むための手法や思考はどんなものかといった研究領域の一端をご紹介いただきました。
ブランドを育てる
――まず初めに鈴木先生のご専門について教えてください。
授業としては、マーケティングとデザインシンキングを受け持っています。研究は、ブランド・マネジメントと消費者行動にまつわるテーマを幅広く対象にしています。
――その中で特に注力されている領域はどういったものでしょうか。
今一番力を入れているのは、ブランディング・ケイパビリティという研究です。ブランドが重要であるという認識は広まってきていますが、日本企業、特にサービス産業においては、実際にブランドを生み育てるとなると、誰がどのように行うのかについては明確に理解しきれていない部分があるのではないかという問題意識をもっています。
ブランドというものは形がなく、実はとらえどころのないものですので、企業でブランド・マネジメントをしようとすると、難しく感じられることも多いかと思います。
ブランディングやマーケティングに関してセンスや優れた能力をもつ社員だけがブランドをマネジメントするというのは企業としてあるべき姿ではなく、ブランドは企業が組織として維持していくべきものだと私は考えています。そういったときに、ブランディングをする上で必要な組織能力とはなにか、このことを明らかにするためにブランディング・ケイパビリティの研究を行っています。
ブランディング・ケイパビリティがグローバル的に新しい研究領域かと言うと、必ずしもそうではありません。どうすれば強いブランドを確立できるのかという問いは、ブランド研究の大家であるデービッド・アーカー先生やケビン・レーン・ケラー先生も書籍にまとめていらっしゃいますし、日本でも翻訳されています。しかし、組織能力(ケイパビリティ)としてどういった能力が必要とされるかについては、研究もまだ途上段階であるため、その意味で価値があると考えています。
――ブランディングやマーケティングの考え方、組織の作り方は日本と海外では異なるのでしょうか。
ブランドの基本的な理論そのものには文化差があるとは思いませんが、日本企業は海外企業と比較して、ブランドをあまり体系立てて戦略的にとらえていないかもしれません。その意味では、日本企業は遅れている部分があると言えるかと思います。
――先日とあるマーケティングフォーラムに参加したのですが、参加者は皆日本人で、マーケティングについては個々人の捉え方や定義があるようでしたが、海外ではいかがでしょうか?
アメリカにはAmerican Marketing Associationという大きなマーケティング団体があり、その団体がマーケティングの定義を定めています。その定義が、一般にどの程度浸透しているかは別の問題としてありますが、一つの指針となっている側面はあります。この定義は、日本でも翻訳されているフィリップ・コトラー先生の教科書等で知られていますので、日本でも一定の共通した定義はなくはないです。
しかし、日本の歴史を紐解いていくと、学問としてのマーケティングが輸入される以前から、マーケティング的な考え方は存在していましたから、整理されずにごちゃごちゃになってしまっている部分があるのかもしれません。
――日本固有のマーケティング的な考え方は比較的感覚的で、学問としてのマーケティングのほうが体系的な整理がされているということでしょうか?
そうですね。アメリカでは、1900年代からマーケティングに対して科学的なアプローチがなされていましたので、体系的な整理がされています。日本では、あえてマーケティングと呼ばなくても、例えば「お客様第一」といった発想は家業で代々受け継ぎ、当たり前になっているところがあります。反面、マーケティング・コミュニケーション領域において、自身が作り上げた価値をお客様に伝えていくことは、日本の伝統的価値観とも相重なって、苦手とする分野になりますので、遅れてしまっている領域かもしれません。
――国内企業でマーケティングやブランディングに関わる人たちはどう考え、どのようにしていけばいいでしょうか?
ブランド・マネジメントに関しては、業界によって浸透度の違いがあるように感じています。消費財や食品、化粧品などはマーケティングやブランディングは比較的進んでいます。
ブランドというと、一般には広告やマーケティング・コミュニケーションのイメージが強いようですが、それだけではありません。ブランディングとは、一言でいうと差別化をつくることですので、人材マネジメントやプロセス・マネジメントも関係がありますし、あらゆる企業の活動と関連すると言っても過言ではありません。これは、B2Bの業態であっても同じです。
つまり、経営者にとって、ブランドとは企業が行っていることを包括的にとらえることができるものになります。
そういった中で、サービス産業においてはマーケティングやブランディングが行われていないわけではないのですが、ブランド認識が狭い(広告やマーケティング・コミュニケーション等に限定されている)ため、ブランドに対する意識が低い傾向にあります。
サービス産業は、これから一層グローバル化されていくことなりますが、海外のサービス産業の企業にはブランド力の強い企業も多く、そういった企業と戦っていかなくてはならなくなります。そのため、これまでブランドを意識してこなかった企業も、あるいはブランドに投資をしてこなかった企業も、これからの時代ではブランドを意識、投資していく必要があります。
経営戦略とブランド
――企業がどこを目指すのかといった経営戦略を明確にすることがブランドを作っていくということはありますか?
そうですね。ブランドはさまざまな要素でできあがっていきますが、その一つには企業のありたい姿、ブランド・アイデンティティと呼ばれるものがあり、企業のミッション(使命)、ビジョン(目指す姿)、バリュー(価値)が大きく関係してきます。その意味では、企業戦略と密接に結びついてきます。
――ミッション、ビジョン、バリューといったものを飛ばしてブランドを作ろうというのはやはり難しいのですか
はい、難しいです。ブランドには形がないため、ブランド・マネージャーたちは企業が考えるありたい姿と市場の考える企業イメージのギャップを埋めていく必要があります。つまり、市場にどのように思われたいのかという部分が抜けてしまうと、ブランドを生み育てるということが難しくなってしまいます。
ブランドとの接し方
――サービス産業でブランディングを上手く行っている企業にはどんな企業がありますか。
インターブランド社が発表しているグローバルブランドのトップ100などを見ると、飲食業ではマクドナルドやスターバックスといった欧米企業が入っています。日本企業からは、自動車メーカーや家電メーカーなどの製造業からの選出が主で、サービス産業からの選出は残念ながらありません。サービス産業自体は、欧米企業が名前を連ねていることからも、ブランド力を持てない業界ということではありません。
――そういった状況の中で日本企業向けにブランディングのご支援もされていると思いますが、まずはどの部分から着手されるのでしょうか。
まずは、経営者層のマインドセットが重要です。ブランドは、お金も時間も人も投資しなければ確立されていかないものなので、会社として戦略的に投資を行っていくように経営者の方に考えていただくことが大事になってきます。そして、企業としてありたい姿を再確認することも大事です。
例えば、東京オリンピックに向けてスポンサーになるといった手法は、露出が増え、認知が広まるので有効ですが、より長期的な目線でどうありたいかを考え、そのために何をすべきかを洗いなおす必要があります。
――ブランドというものを一般社員はどう接していけばよいでしょうか。まずは正しく理解することが重要でしょうか?
ブランドは、経営者のみが意識すればよいものではなく、社員1人ひとりがとる意思決定を通じて体現されていくものなので、全員が理解する必要があります。
――そうなるとブランドが浸透していくためには、人事部門からの教育、あるいは制度の設計などが重要となってくるのでしょうか。
はい。人材教育もとても重要になってきます。
マーケティングとデザインシンキングの関係性
――鈴木先生はマーケティングとデザインシンキングについて教鞭をとられていますが、両者の関係性はどういったものになるのでしょうか?
まずはマーケティングについてですが、私はマーケティングとはCreating and Delivering and Maintaining Values for Customersととらえています。つまり、顧客価値を創造し、提供し、さらに維持していく活動です。近年では、カスタマー・リレーションシップといった購買後の消費者経験価値も重要視されています。提供前から提供後までを含めた、お客様にとっての価値にまつわる活動全般がマーケティングの領域になります。
デザインシンキングについてはさまざまな考え方がありますが、私はヒューマン・セントリック(人間主体)、プロトタイプ・ドリブンで、誰もが予期しなかった形のイノベーションを創造していくことととらえています。
私の中でその二つがどういった関係性にあるかと言いますと、今の時代を踏まえると、相互補完的であると考えています。
マーケティングの授業では、価値の創造、提供、維持に関する教科書的な「型」(フレームワーク)を教えています。しかし、21世紀になり、世の中の変化のスピードはどんどん速くなっていますので、そういった変化の激しい環境下では、フレームワークに沿って戦略的に思考し、価値を作るということは時間がかかり、失敗することもありえます。
一方で、クイック・プロトタイピングとも言われますが、市場やお客様に共感して問題を特定し、問題に対するソリューションを考え、そのソリューションのプロトタイプを作り、ターゲットとするお客様にテストする。これをクイックに行うことが、デザインシンキングです。
マーケティングのフレームワークに沿った手法ですと、届けたい顧客価値を実現するための商品であったり、プロモーションであったりの完成形を作ってから届けるといった順番になりがちです。デザインシンキングでは、完成形を待たず、プロトタイプを実装し、市場の反応を見ながら、繰り返し手を入れ、精緻化していけばいいという考え方で、スピード感が求められる時代には非常にマッチしていると思います。
とは言え、市場やお客様に共感して理解することは、言うは易し、行うは難しです。マーケティングや消費者行動の原理を把握することで、市場やお客様の理解がぐっと深まるので、両者は相互補完的であり、どちらも重要な考え方だと思っています。
――はじめの取っ掛かりを探る精度を上げるためにも、マーケティングは重要であると。
はい、その意味で型が重要と言いました。最終的には、型を破っていくことでよりイノベーティブなものが生まれやすいと思います。21世紀は20世紀のものは当てはまらないと言われることもありますが、人間の根底はそう大きくは変わりませんので、古典には意味があり、これまで培われてきたマーケティングの理論やフレームワークを学ぶことにもまだまだ意義があります。
具体と抽象を行き来する
――鈴木先生はもともと民間企業でのお勤めの経験もありますが、研究と実業の違いは、そしてどう活かしていくべきでしょうか?
アカデミックな視点は企業活動にも役立つと思いますが、アカデミックな理論は抽象化されています。企業の方々は、自分たちの企業のコンテクスト(文脈)に落とし込んで教えてほしいのだと思いますが、アカデミアの立場からすると、その行為(抽象概念を具体化し、自分たちの文脈に落とし込むこと)は、考える力そのものと位置付けられるので、本来はむしろ個人で培うべき能力になります。しかし、具体性があって分かりやすいものが好まれるという実情もあります。
私がMBAで教えているときにも、企業の方の講演を取り入れたり、事例を取り上げたりすると、学生にとっては分かりやすいようで、満足度も高いです。
――抽象化されていない情報で満足してしまうのでしょうか?
その企業で上手くいったことを自分がやろうとしたときに、果たしてうまくいくのかということを常に問い掛けながら聞いてもらいたいのですが、そのまま受けとめてしまうことに懸念しています。
――具体例で教えてもらったことは自身で抽象化し直さないと利用できないからですね。
はい。本当の意味では、自分で抽象化しないと利用できません。そもそも経営は文脈の影響を強く受けているものです。例えば、現在、日本の小売業のトップはイオンさんですが、それは今という時代性、日本という環境、イオンというブランドなど、さまざまな意味で固定化された文脈内での戦略があっての結果です。同じことを別の企業がやっても、おそらく上手くいかないでしょう。つまり経営というものは、極めて個別性が高いのです。これを抽象的に思考できると、不変的な部分を理解でき、転用できるようになります。(学問を実学に活かすためには)具体と抽象を行ったり来たりできるようになることが重要です。
――大学での勉強もまさにそこがキーのように思えます。当時は社会に出てどんな意味があるのか疑問もありましたが、仕事に活かすのは自分で具体に置き直すかどうかにかかっていると。
その橋渡しが得意な組織の一つは、コンサルティング会社だと思います。アカデミアと戦略コンサルタントの違いは経験上意識していますが、コンサルタントはまさにクライアントファーストであり、抽象的なナレッジ(知識)を個別具体性に落としていくことが得意です。
――ブランディングに直接かかわらない従業員にとっても、企業の掲げる理念を読み取り、自分の行動に落とし込む意味では、抽象と具体の行き来は同じく重要になってくるのでしょうか。
そうですね。大事ですね。ブランドというものは、得てして抽象性が残るものになりがちです。普段は、企業のブランド、ビジョン、ミッションなどは忘れているかもしれませんが、会社の一員としてこういう意思決定をとるべきだと考えているときには、抽象的なブランドというものを自身の具体的な意思決定に関連付けているので、やはり抽象と具体の行き来を行っているのだと思います。
――そこを鍛える術はありますか?
ケースメソッドは、そういった意味ではまだ有用だと思います。抽象化して本質を学ぶということは、ケースメソッドでたくさんのケースを学びトレーニングすることで鍛えていくことができます。
鈴木 智子(すずき さとこ)
日本ロレアル(株)、ボストン・コンサルティング・グループに勤務した後、一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士(MBA)、同博士後期課程(DBA)修了し、博士(経営学)を取得。京都大学大学院経営管理研究部特定講師、特定准教授を経て、現在、一橋大学ビジネススクール国際企業戦略専攻准教授。
専門は消費者行動論、国際マーケティング、ブランド・マネジメント。
経済産業省「グローバルサービス創出研究会」委員、経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員、中小企業庁「尾州TASAI委員会」委員、株式会社三菱総合研究所「東京ホスピタリティプロジェクト ビジョン策定委員会」委員、等を歴任。
国内外の学術雑誌で、多数の研究論文を発表。主な著作に、『イノベーションの普及における正当化とフレーミングの役割』白桃書房(2013)がある。
連絡先:ssuzuki@ics.hub.hit-u.ac.jp